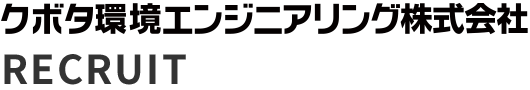プロジェクトの根幹を描く設計
建築と社会貢献の両立が魅力

設計職・入社10年目
学生時代から建築に興味を持っていて歴史的な住宅などについて研究をしていました。現在は水処理建築部建築設計課に所属し、水処理プラントの土木建築工事の設計担当として、お客様の要望を実現するため、設計事務所や下請け業者の方々と連携しながら、プロジェクトを円滑に進める役割を担っています。 建築に携わりながら、社会インフラという基盤づくりに関わる点に魅力を感じて入社を決意。仕事の魅力はなんといっても大好きな「建築」が社会貢献につながること。先輩にも恵まれ、地域住民に認めてもらえる施設を作り続けたいと思っています。
水処理プラント|し尿・汚泥再生処理施設
し尿・浄化槽汚泥などを浄化して河川や海へ放流する施設
プラントとプロジェクトの理想の姿を描く
この仕事に就きたいと思った理由は?
環境プラントは生活インフラでなくてはならない建物です。以前から建物を建てるだけでなく、社会に貢献したいという思いも少なからずあったので、この二つの軸を一緒にできるのはここしかないと思い、この仕事に就きました。
水処理をする施設というのも魅力です。まずプラント(処理をする機器や設備)があって、それを収める建物なので、機械が変われば「建築」も応えるといったところが面白いです。
そしてこの仕事の魅力は全国の地域を相手していることとその規模の大きさです。
たとえば、水処理プラントでは、二次製品で作れないような規模の水槽を作ります。その環境に応じて唯一の構造物を作るんです。
※ニ次製品:
一次製品(原材料や素材)を加工して作られた製品のことを指します。
具体的な仕事の内容を教えてください。
設計には案件を受注するための計画設計と受注後の実施設計があり、主に実施設計を担当していました。実施設計では、その根幹となる計画をお客様と決めて、設計事務所に具体的な設計の依頼や指示を出す段階まで持っていきます。
たとえば、窓の仕様を1枚1枚決めたり、建築機械設備、排水とか空調、さらに断熱の素材や厚みまで計画して指示をします。
私たち建築担当の仕事は箱を作っていくイメージです。
こういう処理フローにするのでここに穴が欲しいとか、ここに機械を乗せたいとなれば、穴を開ける計画だったり、機械が乗っても大丈夫な構造にしておくといった設計をします。
プラントの処理や機器と密接に関わっている建物なので、機械が変われば建築担当も柔軟に対応して設計をしていきます。そういうところが面白いです。

スムーズな連携がプロジェクトの要
業務はどのように進めていますか。
最初は営業担当が中心となって、そこに計画部隊の、土建、プラント設備、電気設備の設計メンバーが携わって内容を固めていって受注します。
受注後は、それぞれ実施部隊の設計メンバーにバトンタッチします。
実施設計が完了した後は工事の担当がメインとなって工事が始まるといった感じです。
私自身はプラント設計の担当者とのやりとりが一番多いのと、現場も多いです。現場の所長だったり。
プラントの設計と建築物の設計をうまく合わせてひとつの施設にしなければならないので、整合性の確認や、要望などを調整したりします。工事が始まっている現場では、図面に落としきれなかったことをどうするかといったやりとりが結構多いですね。

面白さと責任を感じる
どんなところで自分らしさが発揮されますか。
これまで広島の府中市を一番最初に担当して、その後に北海道森町、次に千葉南房総市、そして今は徳島県吉野川の案件をやっています。
プラントの基本的な処理方法やフローの概念はありますが、独自性や自分ならではの意匠も盛り込むことができます。
特に計画設計では自分の裁量で「この窓を連続してつけたい」とか、そういうことができるのが楽しいですね。「あの建物かっこいいな」とか、「あの建物いいな」と常に見ていて、インスパイアされたりもします。
最終的には素敵な建物にしたいです。なかなか実現は難しいかもしれないですけど。
どんな魅力がありますか?
ひとつは規模感です。何十億円ものプロジェクトに携われるスケール感のある仕事だと思います。関与するプロジェクトが社会に与えるインパクトを実感できるというのが非常にやりがいを感じます。もう一つは、全国のプラントが相手なので、一つとして同じものがないところです。
たとえば北海道の施設では壁の内側に断熱材を貼る工法では熱が部屋内に入るリスクが高いので、建物全体を断熱で囲ってしまう外断熱工法というちょっと珍しい工法を採用しました。
そんなふうに地域の設計事務所と連携しながら情報収集して、地域の状況に応じて設計します。
感覚的な話になりますが、元々なかった場所に私たちが作っているのは、その地域に住んでいる人に少なからず影響を与える建物なのだと思っています。
プラントは完成すると30年から40年ぐらいは動かして使っていきます。それに応える責任も感じています。

ダイナミックかつ繊細が醍醐味
特に気をつかっていることは?
一番はやはり構造です。
いろいろな条件を全部入れて構造計算を流しているので、条件が変わってしまうと、いろんな部分に派生してしまいます。その辺の落とし込みの誤差や差異が生じないように、プラント設計の方にも適宜確認をしながら進めています。
それと継続して進行する業務への気配りを意識しています。実際の業務ではプラント設計から準備段階の情報をもらって建築設計が走り、その後にプラント設計が走ります。最初から全部を落とし込んでいない状況で並行して走りながら、発生する変化に柔軟に対応していくイメージです。
プラント設計の仕様を受け取って建築していくだけではなく、建築側からも提案していきます。
一番大きいのは動線です。どういう風に人が動いていくかを仮定して、最短で部屋に行けるように、この部屋はこっちにずらしておこうとか、配慮をします。作業動線上に洗面台を設けることもあります。
さらに、水槽に入るためのマンホールを開けるときに安全帯を掛けることができるようなフックを設けておくといった細かい点まで気を配ります。
大きな建物に緻密な気遣いを散りばめていく。
「設計」の大切な仕事だと思います。